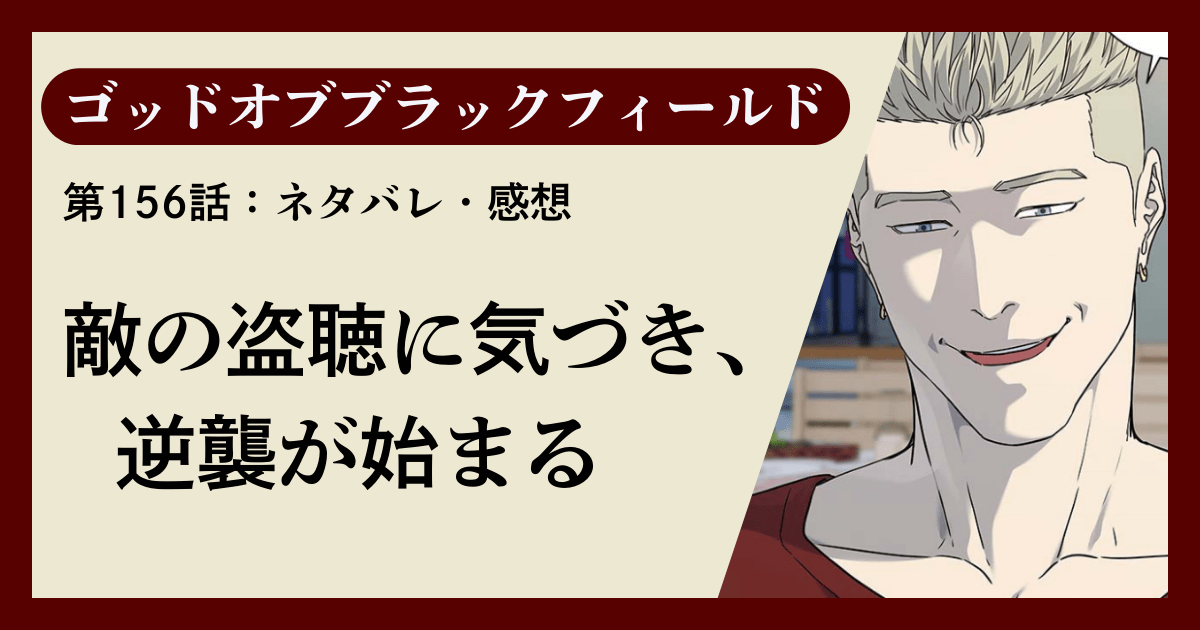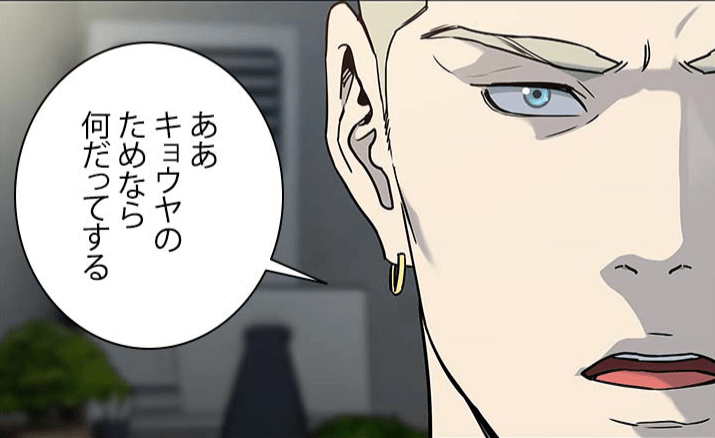※本記事は『ゴッドオブブラックフィールド』第156話のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。
前回の第155話では、黒川が極秘作戦のためモンゴルへと向かい、恭弥はその出発を見送るという静かな別れが描かれました。
一方で、スミセンを通じて清水グループの影が再び浮上し、「情報戦」への突入が示唆される展開もありました。
今回の第156話では、敵の監視網が恭弥たちの足元にまで迫っていたことが明らかになります。その中で恭弥が取った行動とは…そして、女たらしのスミセンが担う意外な役割とは?
見どころ1:盗聴はもう始まっている――静かに仕掛けられた罠
スミセンが恭弥に話したかったことは、「ゴント自動車日本支社の持分を高く買う」という人間が現れたということだった。しかも、申し出てきたのは清水グループ所属の弁護士。
最初に感じたのは、「ゴント社の株を買うことで、何か経営権などを奪って良からぬことをしようとしているのでは?」という不穏な気配だった。
しかし恭弥は、もっと本質的な異変に気づいていた。
弁護士が「本社の許可がなければ売れない」という基本すら知らずに持ちかけたその動きが、逆にあやしいと判断する。
恭弥のスマホ「スミセン、靴と携帯をオレに渡せ。あとは二人でくだらない話をしてろ」
©Kakao piccoma Corp.
傭兵時代をともにした仲間たちの間に、言葉はいらない。
恭弥のサインひとつで動いた作戦は、喫茶店の片隅に置かれた紙袋、スミセンの靴、スマホ…そのすべてから盗聴器が発見される結果に。
- 盗聴器の性能は、半径2kmまで録音可能という超高性能
- 京極の部下の調査でスミセンの自宅も調べることに
- 清水グループが誰を監視しているのか、その範囲まで見えてくる
まさに「監視はすでに始まっていた」状況の中、恭弥は冷静に一手を打つ。
相手が仕掛けた「見えない罠」を逆に利用する発想が、まさに“ゴッド・オブ・ブラックフィールド”の異名にふさわしい場面だった。
とぼけた掛け合いを挟みつつも、その裏で恭弥は、次なる攻撃の布石を着々と打っていたのだった。
見どころ2:女遊びが武器になる?スミセンと仕掛ける“逆転の諜報作戦”
盗聴器が発見されたことで恭弥は守りから攻めに転じる。
恭弥が目を付けたのは、喫茶店で明らかになったスミセンの“女たらし”ぶりだった。
西恭弥「曜日別に会えば6人と付き合えるだろ?」
©Kakao piccoma Corp.
いつもの軽口かと思いきや、その“モテ力”は情報戦において大きな武器となる。
恭弥はスミセンにある「リスト」を渡す計画を立てる。そこに載っているのは、なんと…
- 全員「周防裕三の女」
- 清水グループの会長に繋がる人物たち
- その人間関係の“裏”を探るための工作対象
スミセン「キョウヤのためなら何でもする」
©Kakao piccoma Corp.
そう言い切ったスミセンに、恭弥は今回の「色仕掛け諜報作戦」を託す決断をする。
- 軽薄な女好きに見えるスミセンだが、ここでは誰よりも任務に適した人材
- 普通の捜査では近づけない“周防の女たち”に、唯一自然に近づける存在
- 女遊びという“弱み”を、逆に武器に変えた恭弥の判断力
スミセン「オレがそんな簡単にやられるとでも?」
©Kakao piccoma Corp.
西恭弥「…昔みたいに戦えないって言ってただろ」
戦場に立てないスミセンは、別のフィールドで役割を果たす。その姿勢に、恭弥も内心では大きな信頼を寄せているように見えた。
“戦えない者”に託された任務が、今後どのような影響をもたらすのか?これは「肉弾戦ではない戦い」の始まりを予感させる。
まとめ:ゴッドオブブラックフィールド 第156話
第156話は、恭弥の戦いが情報戦のフェーズに突入したことを印象づける回でした。
スミセンに仕掛けられた盗聴という静かな攻撃を、恭弥は即座に見抜き、逆にそれを足がかりとして敵の内側に食い込もうとします。
特に目を引いたのは、「女好き」というスミセンの欠点すらも、諜報の武器として利用する恭弥の冷静さです。
一方で、スミセン自身も「キョウヤのためなら何でもする」と覚悟を見せる場面があり、彼の信頼関係の深さも垣間見えました。
派手な銃撃戦はないものの、今後の展開に直結する静かな駆け引きが繰り広げられた1話だったと感じました。
- 次回記事:157話:恭弥、黒川の作戦を信じて待つ
- 前回記事:155話:黒川との別れ、ダエルへの誓い
- 総リンク:『ゴッドオブブラックフィールド』全ての感想記事リンク一覧
- 用語記事:登場人物・主要キャラ・用語まとめ