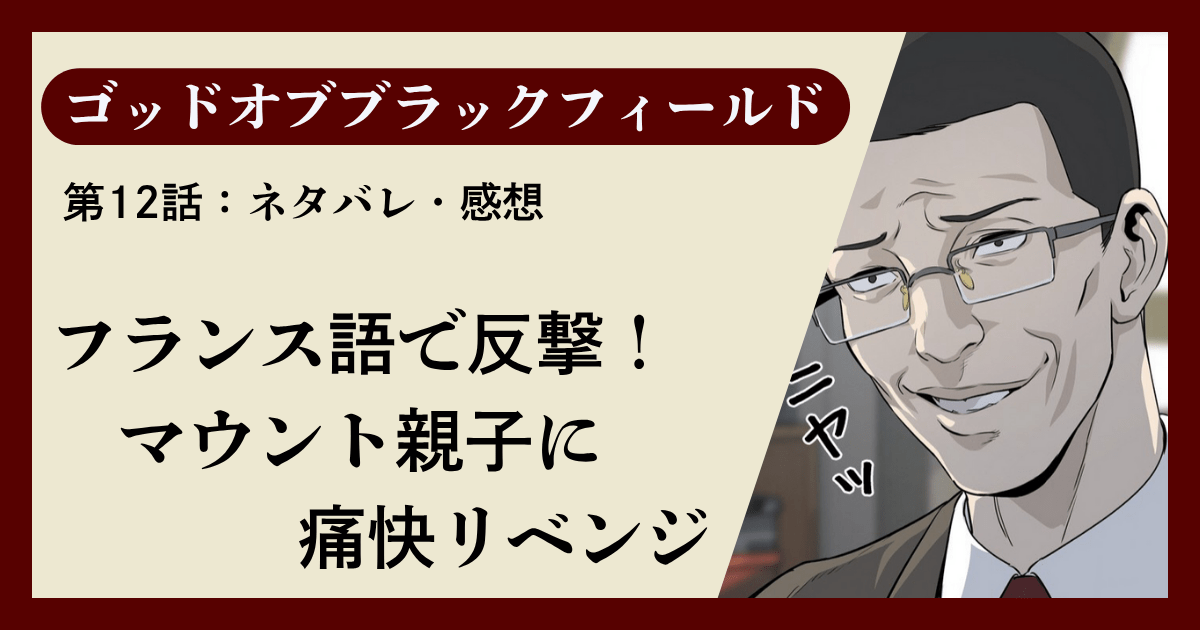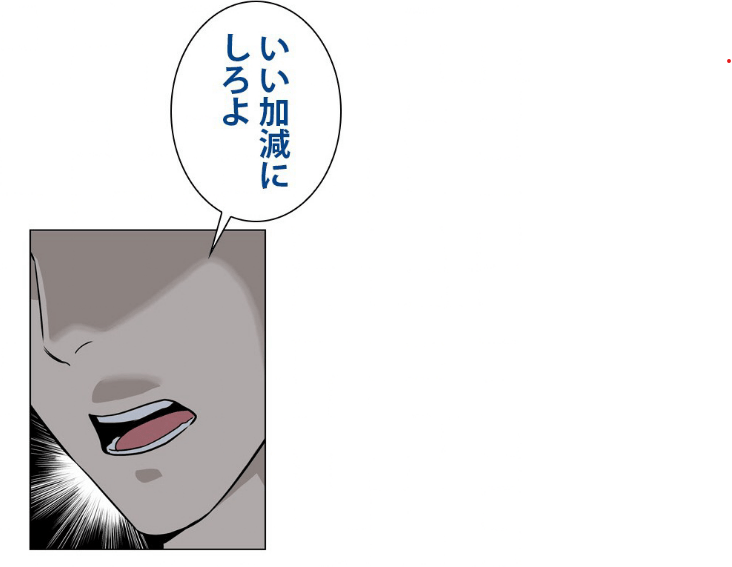※本記事には『ゴッドオブブラックフィールド』第12話のネタバレが含まれます。未読の方はご注意ください。
第12話では、恭弥の“日常”と“家庭”に焦点を当てたエピソードが展開されました。
かつての肉体に追いつけない自分に苛立ちながらも、母のために時間を割く恭弥。
さらに、母親をバカにする相手に対しては、フランス語を使ったスマートな逆転劇でしっかりと仕返しを果たします。
今回はそんな彼の“戦わない強さ”と、人としてのバランス感覚が光る回でした。
見どころ1:鍛錬の限界と、母への気遣い
転生後の肉体をどうにか鍛えようと、自室でトレーニングに励む恭弥。しかしその体は、自分がかつて持っていた戦闘能力には到底及ばず、すぐにバテてしまいます。
恭弥(クソッ 頭ではわかってても弱くて遅いこの体がついてこねぇ。こんな状態で…やりあえるのか?)
©Kakao piccoma Corp.
この場面では、彼の焦りと苛立ちが痛いほど伝わってきました。
「戦えないこと」に対する恐れは、命を預かるリーダーとしての責任感から来ているのだと思います。
普通の高校生にとっては“筋トレがきつい”程度の話かもしれませんが、恭弥にとっては“生き残るための必須条件”です。
それだけに、この描写には重みがあります。
そんな彼の思考を中断するように、母が部屋をノックします。話の内容は、「母の友人とその息子と一緒に、フランス人経営のレストランでブランチをしないか」というもの。
母の表情には「もし無理ならいいのよ」と言わんばかりの遠慮が見えます。
そして恭弥は、逡巡の末、こう答えます。
恭弥「大丈夫です。行きます」
©Kakao piccoma Corp.
ここで私が印象的だったのは、恭弥の回答です。実際は行きたくない、鍛錬したい、焦っている——そんな本音はあったはず。
それでも母の気持ちを思いを優先した。
彼は家庭に戻れば、ただの「息子」であり、そこには恭弥なりの“守るべきもの”がある。
冷静な判断とやさしさ、その両方を持っているからこそ、彼はリーダーなのだと思いました。
見どころ2:フランス語での“逆転劇”とマウント親子との決着
恭弥が母と共に訪れたのは、フランス人が経営するおしゃれなレストラン。母の友人である育子とその息子・優とのブランチが目的でした。
しかし始まって早々、育子親子の“教育マウント”が全開に。優のフランス語を「すごいでしょ?」と自慢し、恭弥の母に「塾も通わせていないなんて信じられない」と畳みかけます。
挙げ句、母親が「恭弥も少しフランス語が話せる」と言えば、育子は「ネットで独学?」と笑い出す始末。横でそれを見ていた恭弥は、静かにフランス語で言い放ちます。
恭弥「いい加減にしろよ」
©Kakao piccoma Corp.
この瞬間、空気が一変しました。
この場面は、単なる語学力のアピール以上に、「言葉を武器にした戦い」だったように思えます。
恭弥は力で押さえつけず、冷静に言葉で逆転する——このスタイルは、彼の頭の良さを感じさせました。
さらに驚くべきは、その会話を聞いていた隣のフランス人女性たち。恭弥のフランス語に興味を示し、話しかけてくるのです。
ミシェルたちは、「あなたに興味がある」「連絡先を教えて」と自然に距離を詰めてきます。
ミシェル「連絡先」
©Kakao piccoma Corp.
育子たちが席を立って去っていくのと対照的に、フランス人女性たちは恭弥に好意を見せ、状況は完全に逆転。
母親を侮辱された恭弥が、「フランス語」と「行動」で見事に仕返しを果たした一連の展開は、読んでいてとても爽快でした。
この場面を通して、「本当に強い人は感情に流されず、必要な場面で力を発揮する」——そんな恭弥らしさを確認できた気がします。
まとめ:ゴッドオブブラックフィールド:第12話
第12話では、恭弥の“現在”と“過去”が交錯するような二つの場面が描かれました。
鍛錬に苦しむ姿からは、かつての強さを取り戻したいという焦りが、そして母とのやり取りからは、息子としての優しさと配慮がにじみ出ていました。
また、ブランチの席では教育マウントを取ってくる相手に対し、恭弥はフランス語という武器で見事に返り討ち。母を守るために動いたその姿に、彼の本質的な“強さ”を感じました。
私には、“戦えない今の自分”と、“守るべき日常”の間で揺れる恭弥が、とても人間味のある存在として映りました。
- 次回記事:13話:ヤクザの事務所に単独突入!恭弥の強さと覚悟
- 前回記事:10、11話:やることが増えていく西恭弥
- 総リンク:『ゴッドオブブラックフィールド』全ての感想記事リンク一覧
- 用語記事:登場人物・主要キャラ・用語まとめ